大饗の地名は、古くは「続日本紀」天平神護元年(765年)10月28日条に称徳天皇が紀伊国行幸の帰途、河内国丹比郡に至ったとの記事があり、この時、当地が饗宴の場となったので地名が生まれたと言われている。
大饗は古代、丹比郡に属したが平安時代後期以降は分立した八上郡に属し、弘安9年(1286年)の金剛寺(現河内長野市)、応永元年(1394年)の西琳寺(現羽曳野市)寺領田畠関係目録文書に「田井御庄大饗郷」、「正税分、但大饗郷内在之」が見られる。
大饗郷は鎌倉期〜室町期に見える郷名で西除川中流左岸に位置し、東西大饗村、菩提村と一村を形成、西は枝郷引野(現引野町)に至る。寛政二年(1790年)「東西大饗村・東西菩提村立会麁絵図」(都立中央図書館加賀文庫蔵)に、菩提村の北西部、菩提村枝郷「大饗野」と記される集落が見られる。
このことから、大饗野は大饗郷の枝郷であったが、その後分村し、菩提村の枝郷となったと考えられる。
大饗村は東西の大饗村と菩提村の総称で、江戸時代初期には既に三村に分立していたと思われる。水利関係などでは一括して大饗村として扱われた。
明治6年の地引絵図(壇野家文書)には三村の村領が各集落周辺部を除き、錯綜地として描かれている。
 参照:「日本地名大辞典27巻」「日本歴史地名体系28巻」「大阪府全志第四巻」より
参照:「日本地名大辞典27巻」「日本歴史地名体系28巻」「大阪府全志第四巻」より
|
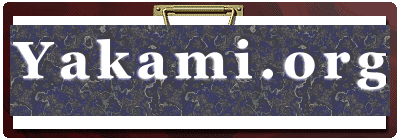 堺市美原区八上校区自治連合会
堺市美原区八上校区自治連合会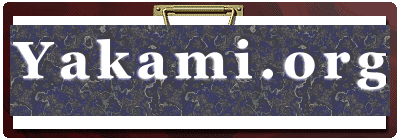 堺市美原区八上校区自治連合会
堺市美原区八上校区自治連合会